古民家の再生 高槻 古民家

お座敷も含め、6つある和室が全て差鴨居という堂々たる民家です。
一番の目的は、建物のいがみ直しと構造補強です。
今回は、工事前の写真と工事後の写真と同じアングルで並べて表示しています。ご参考になれれば幸いです。
古民家の構造改修(改修前と改修後)
伝統木工法による 構造材を活かした改修

左手の縦繁格子戸は再利用。右手正面の大荒硝子桟戸もシールをめくって清掃し再利用。柱を3~5cmほど上げたため、既存のタイルとの間に隙間ができ、モルタル巾木で埋める。
壁は白漆喰塗。木部はワビスケ塗り。右手建具と敷框のみオスモマホガニー塗。

梁と柱の垂直水平が綺麗にでています。
構造材を美しく見せる和風建築のよさが表れた空間です。
床下は、フェノバボード50mm+土間コンクリート250mm。
壁は全て白漆喰塗。
畳は熊本産本井草です。

両脇の建具は手前も奥も再利用。柱を真っ直ぐにしたため、高さが足らなくなり、足元に20mmほど木材を足しています。
正面に見えるのはキッチンの対面カウンター。天窓の光だけで充分明るくなっています。

座敷のすぐ北側に寝室があります。
箪笥置き場の窓を大きくとり、硝子面の大きな建具にしたので、とても明るくなりました。襖を舞羅戸に替え、押入内をクロゼットに改修しています。

ここは、竿縁天井だったのですが、小屋裏の床組を見せる事にしました。
もともと、四方とも、右手の梁と同じ高さに梁がぐるっと回っていたのですが、同じ尺2の梁を高い位置に入れ替えています。正面の桟戸の向こうが寝室。左手の明るい空間が台所です。天窓の光がダイニングに降り注いでいます。



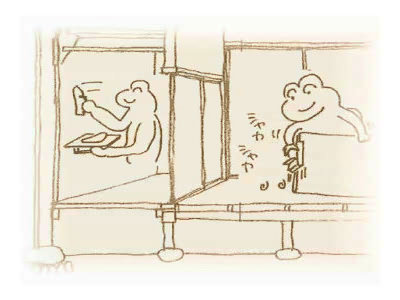

外壁や屋根がリフォームされていたので、だいぶ心配しましたが、外壁の大きな剥離もなく、瓦の暴れも補修程度で収まりました。また、工事中に断熱材が不足しましたが、これもなんとか集めることができました。いろんな事が上手くいき、ほっとしています。
解体・基礎・設備・左官・塗装、そして大工… さまざまな職方の技を活かして建物を元の状態+快適な空間に作りかえることができました。本当によかったなと思っています。