 京町家や大工の歴史と文化を知りたい方
京町家や大工の歴史と文化を知りたい方



当社は、建築工事業を営んでおりますが、木造住宅を残し、町並みを守っていくために様々な活動をしています。
1人でも多くの方に、木造住宅の良さ・古い建物の価値・大工さんの技術を知っていただきたいと考えているからです。
ご要望に応じて、古いお住まいの改修現場やお施主さんのお住まいの見学もしていただく事もできますし、大工さんの仕事をお伝えする講演会なども実施しています。お気軽にお問い合わせください。
業務の合間になりますので、少し余裕をみてお問い合わせください。また、見学はお施主さまの了解がいります。遠方の方の場合は、メールや電話になりますのでご了承願います。
京町家や古民家
- 研究団体
- たくさんの団体が活動されていますが、京都では、京町家再生研・京町家作事組・古材文化の会などがあります。
京町家・古民家活動団体の概要はこちら - 京町家模型
- 1/10、1/20の模型が全部で4体。仕口や収まりなども正確に再現。TV番組やイベントに何度も貸し出しをしています。
- 全国の町家『住まいは文化』
- 当社会長が白井貴子さんと一緒に全国の町家を訪ねた番組の記録です。北海道から沖縄まで10ヶ所をまわり、先人たちの知恵を紹介しています。
大工技術
- 新聞記事『職人今昔』『職人随想』
- 当社会長が建設協同組合と全国商工新聞に連載した記録です。専門用語で解らないところがあれば、お問い合わせください。
- 単行本『町家棟梁』
- 副題は「大工の決まりごとを伝えたいんや」。京都工芸繊維大学の矢ヶ崎先生が、当社会長にヒヤリングした内容をまとめたものです。当社会長の人生と町家の歴史が重なります。
- 木組『継手と仕口』
- 当社にて実際に作った写真をアニメーションGIFで紹介しています。継手7種類。仕口5種類。解説付です。
問い合わせ事例
『NPO法人事務局 Sさん』
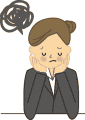
「先達の口伝」と題して、木造建築の決まりごとと心得を学ぶ講座の講師を探しているのですが。

わかりました。手書きの図面をもとに、墨付けから始まって、京町家の屋根勾配の決め方、土壁の下地の編み方などを解説します。一緒に頑張って勉強しましょう!

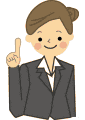
3回にわたって教えていただきありがとうございました。細かな歩掛りまでよどみなく語る棟梁の知識に感心しました。
『番組制作会社 Aさん』
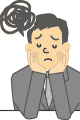
アラキ工務店さんでは5年で墨付けができないと一人前になれないとか。崖っぷちで頑張ってる若い大工さんの取材をしたいのですが。

了解しました。では、仕事の邪魔にならない範囲で取材してください。彼が仕事をしていく上での励みになったら嬉しいです。
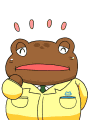
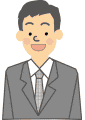
大変勉強になりました。人を育てるというのは大変なんですね。こうして頑張っている若者をみると励みになります。
BS日テレ「キズナのチカラ」放映記録はこちら(音声が出ます)



